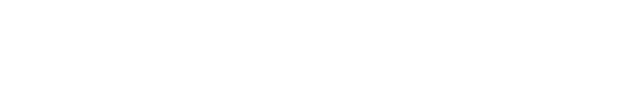自己免疫性胃炎
抗胃壁細胞抗体や抗内因子抗体などの自己免疫機序により、胃体部を中心とした胃底腺領域にびまん性の慢性炎症を引き起こして萎縮性変化を来たします。壁細胞の破壊により高度の低酸状態となりますのでD細胞からの抑制が解除されて、前庭部の炎症を免れたG細胞からのガストリン分泌が増加、髙ガストリン血症をきたしてECL(enterochromafin-like)細胞が刺激され、ヒスタミン放出が促進されます。しかし壁細胞からの酸分泌は亢進しませんのでガストリンの刺激が持続してECL細胞は内分泌細胞過形成(endocrine cell hyperplasia:ECH)を来たし、その過形成からさらに内分泌細胞微小胞巣(endocrine cell micronest:ECM)が形成されて、胃カルチノイド腫瘍や胃がんの発生に関与するとされています。抗内因子抗体により内因子の分泌が低下してビタミンB12の吸収が阻害されると悪性貧血も来たします。低酸から鉄吸収障害により鉄欠乏性貧血を合併したり、経過中にⅠ型糖尿病、自己免疫性甲状腺疾患を併発することもあります。ピロリ菌による慢性胃炎では慢性炎症が幽門腺領域から始まり前庭部中心に萎縮を来たすことと対称的に自己免疫性胃炎では幽門腺領域に萎縮が起こりませんので逆萎縮パターンと称されています(自己免疫性胃炎とピロリ菌による慢性胃炎が合併している場合は胃体部と前庭部とも、すなわち胃全体に萎縮性変化をきたす汎萎縮性胃炎を示します)。また自己免疫性胃炎による胃体部の萎縮は粘膜の中層以下の胃底腺の破壊によるもので、病初期には表層の腺窩上皮には炎症の影響が少なく、ピロリ菌による慢性胃炎に比して表面の粘膜模様に萎縮性変化が及び難いとされています。